フリーランス必見!家事関連費とは?家事按分の割合・目安と節税ポイント
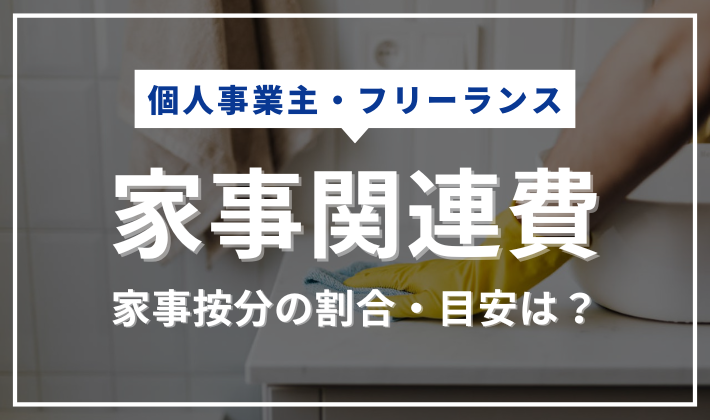
自宅を事務所として使うフリーランスや個人事業主にとって、家賃や光熱費、通信費など「生活と仕事の両方に関わる費用」をどう経費に計上するかは大きなポイントです。
これらは「家事関連費」と呼ばれ、正しく「家事按分」することで必要経費として認められる場合があります。
ただし、割合の決め方や目安を誤ると、税務調査で指摘を受けるリスクもあります。
この記事では、家事関連費の基本から按分割合の考え方、具体的な経費ごとの目安までわかりやすく解説します。
- 家事関連費・家事費・必要経費の違い
- 家事按分のルールと割合の決め方
- 水道光熱費・通信費・家賃などの具体的な按分目安
- 税務調査で指摘されないための注意点
家事関連費とは?|必要経費・家事費・家事関連費を整理
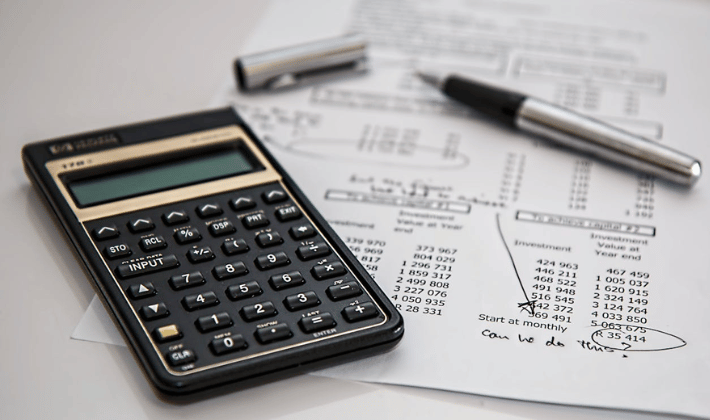
個人事業における必要経費って?
個人事業主やフリーランスが所得を計算する際の必要経費は、別段の定めがあるものを除き、次の金額となります。
- 総収入金額に対応する売上原価その他総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
家事費とは?必要経費との違い
家事費は、一般的に、生活上の費用全般を指し、必要経費には算入されません。
たとえば、食費や娯楽費、生命保険料、所得税などの税金などは、必要経費には含められません。
具体例- 自己または家族の食費や被服費、医療費、娯楽費などの生活費
- 自己または家族の住宅に係る地代家賃、水道光熱費、修繕費、租税公課、火災保険料
- 自己または家族の生命保険料
- 自己または家族の税金(所得悦、住民税、贈与税など)
- 自己または家族の悦金の滞納による延滞税および延滞金
家事関連費とは?事業と生活が混在する費用
自宅兼事務所で仕事をしていると、家賃・光熱費・通信費・車のガソリン代など、生活と事業の両方に関わる支出が必ず発生します。
これらを「家事関連費」といい、合理的に区分(家事按分)すれば経費にできます。
具体例- 自宅兼事務所の家賃や光熱費
- 仕事にも私用にも使うパソコンやスマートフォン
- 自家用車を仕事の移動に利用する場合のガソリン代
家事関連費を必要経費に算入できる条件
この家事関連費については、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額は、必要経費に含めることができます。(所令96)
ポイント- 業務の遂行上直接必要であること
- 必要である部分を明らかに区分することができること
家事関連費の按分ルール|どのように割合を決める?
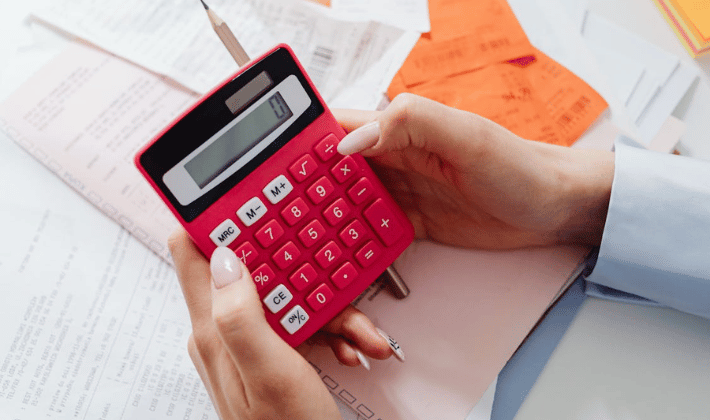
明確な基準は法律で定められていない
家事関連費について、その業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することが心要であることは先に述べたとおりです。
ただし、家事関連費の按分については、法律や通達で「〇%にしなければならない」という明確な基準は設けられていません。
そのため、合理的な根拠をもとに自分で割合を設定することが実務上のルールになります。
按分方法の一般的な考え方
家事関連費を按分する際は、以下のような客観的な指標をもとに割合を算出するのが望ましいです。
- 床面積割合:自宅の中で仕事に使っている部屋の面積 ÷ 全体の床面積
- 使用時間割合:1日のうち仕事で使った時間 ÷ 総利用時間
- 利用状況割合:コンセントの数、回線の利用明細、走行距離など
たとえば、自宅の50㎡のうち10㎡を仕事部屋として利用している場合は、家賃などを、20%(10㎡÷50㎡)で按分する、といった考え方です。
家事按分できない費用に注意
- 生計を一にする親族への支払い:生計を一つにする配偶者やその他の親族に支払う地代家賃や給与賃金は、原則として必要経費にはなりません。(青色事業専従者給与を除く。)
- 税金・罰金など:所得税や住民税、罰金などは必要経費にはなりません。また、公務員に対する賄賂なども経費にできません。
- 純粋な生活費:食費、レジャー、習い事などは事業と直接関係のない家事費として扱われ、必要経費にできません。
- 交際費:業務の遂行上直接必要なものは必要経費に算入されますが、それ以外のものは算入されないため、按分計算する性質のものではありません。
按分割合の目安|水道光熱費・通信費・家賃などの具体例
 家事関連費を経費にする際には「合理的な割合で按分する」ことが必要ですが、具体的にどの程度を経費とすればよいのか迷う方も多いでしょう。
家事関連費を経費にする際には「合理的な割合で按分する」ことが必要ですが、具体的にどの程度を経費とすればよいのか迷う方も多いでしょう。
ここでは、代表的な費用ごとに実務でよく用いられる目安を解説します。
家賃(自宅兼事務所)・住宅関連費を按分する方法
 自宅を仕事場として利用している場合は、床面積の割合で按分するのが基本です。
自宅を仕事場として利用している場合は、床面積の割合で按分するのが基本です。
家賃の家事按分の計算例
- 自宅の総面積:60㎡
- 仕事専用スペース(書斎など):20㎡
- 按分割合:20㎡ ÷ 60㎡ ≒ 33%
水道光熱費(電気・ガス・水道)を按分する方法
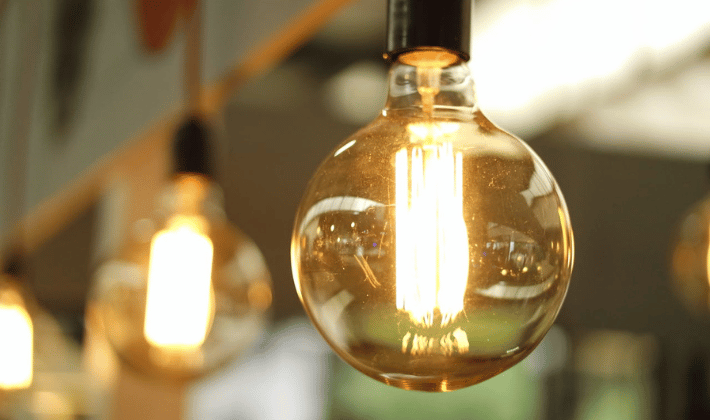 水道光熱費は、床面積の割合と使用状況に応じて按分します。
水道光熱費は、床面積の割合と使用状況に応じて按分します。
- 書斎でのパソコンや照明などの電気使用:床面積割合×使用時間割合
- ガス・水道 :業務利用が少ない場合は按分対象外になることが多いです。
電気料金の家事按分の計算例
- 自宅の総面積:60㎡
- 仕事専用スペース(書斎など):20㎡
- 業務時間:平日・平均労働時間8時間
- 按分割合:(20㎡÷ 60㎡)×(5日÷ 7日)× 1/2 (*1)≒ 11%
(*1) 1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて、均等に電気料金が生じていると仮定し、次のとおり算出しています。
- 1日:24 時間
- 平均睡眠時間:8時間(「平成28年社会生活基本調査」(総務省統計局)で示されている7時間40分を切上げ)
- 法定労働時間:8時間
- 1日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合:1/2
通信費(インターネット・Wifi・スマホ)を按分する方法
 通信費は、仕事と私用の使用比率をもとに按分します。
通信費は、仕事と私用の使用比率をもとに按分します。
通信費の家事按分の計算例
- 業務時間:平日・平均労働時間8時間
- 按分割合:(5日÷ 7日)× 1/2 (*1)≒ 35%
車両関連費(ガソリン代、駐車場代、自動車保険料など)を按分する方法
 自家用車を業務で使う場合、走行距離や使用日数をもとに按分します
自家用車を業務で使う場合、走行距離や使用日数をもとに按分します
車両関連費の家事按分の計算例
- 年間総走行距離:10,000km
- 業務利用距離:3,000km
- 按分割合:3,000km ÷ 10,000km = 30%
税務調査で指摘されないためのチェックポイント
 家事関連費を経費に計上する際、もっとも注意すべきは税務調査で否認されないかどうかです。
家事関連費を経費に計上する際、もっとも注意すべきは税務調査で否認されないかどうかです。
調査官に合理的な説明ができなければ、過去の経費が否認され、追徴課税や加算税が発生するリスクがあります。
按分計算の根拠を明確に説明できるようにする
床面積割合や走行距離、使用時間など、客観的な基準をもとに計算することが大切です。
「なんとなく半分くらい」など感覚的な割合では認められませんので、ご注意ください。
記録や資料を残しておく
税務調査では、「その支出が業務に必要だったか」を確認されます。
以下のような資料を保存しておくと安心です。
- 携帯電話の通話明細や利用明細
- 車の走行距離メモやETC利用記録
- 電気代やガス代の請求書と按分計算表
- 仕事部屋の写真や間取り図
家事関連費・家事按分に関するよくある質問
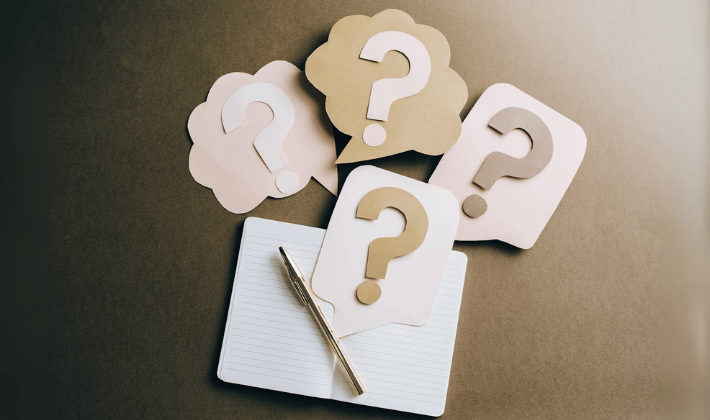
家事按分の割合に明確な基準はありますか?
法律で定められた一律の「〇%」といった明確な基準は設けられていません。
「床面積」「使用時間」「利用状況」など、客観的に説明できる基準をもとに算出する必要があります。
例えば、自宅の一部を仕事用に利用している場合は床面積割合で、車なら走行距離割合で計算するのが一般的です。
青色申告と白色申告で家事按分の扱いは違いますか?
実務上、扱いに大きな違いはありません。
自宅の一室を仕事で使っている場合、減価償却費も経費にできますか?
はい、可能です。ただし条件があります。
- 業務利用部分が床面積などで明確に区分できること
- 実際にその部屋を業務専用として使用していること
例えば、自宅の一室を事務所として明確に区分している場合には、減価償却費や固定資産税を按分して経費計上できます。
逆に、その一室が事務所部分として明確な区分がされておらず、単に経理作業を自宅でしている程度であれば、必要経費に算入することは難しいと思われます。
家事按分後の取得価額が10万円未満なら、減価償却は不要ですか?
判定は「家事按分前の金額」で行います。
家事按分前の本来の取得価額が、10万円以上であれば、原則、減価償却が必要です。 一括償却資産、少額減価償却資産の特例についても、家事按分前の取得価額で判定してください。
まとめ|合理的な根拠を示して安心して経費計上しよう
 フリーランスや個人事業主が自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費、通信費など「生活と事業が混在する支出」が必ず出てきます。
フリーランスや個人事業主が自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費、通信費など「生活と事業が混在する支出」が必ず出てきます。
これらは家事関連費として、業務に必要な部分を合理的に区分すれば経費に含めることができます。
まとめ- 家事関連費は合理的な基準で按分する(床面積・使用時間・走行距離など)
- 税務調査では「根拠を説明できるかどうか」が重要
大切なのは「どのくらいの割合で経費にしたか」よりも、その割合をどうやって導き出したのかを説明できるかです。
家事関連費の処理はやや複雑ですが、正しく理解しておくことで、節税にもつながり、安心して事業に集中することができます。
合理的な根拠を持って、経費計上を行いましょう!

石田 航平(税理士/経営心理士)
石田航平税理士事務所/イナステラ総合会計事務所 代表
元国税専門官。Big4税理士法人を経て、現在は、売上改善・創業支援に強みを持つ税務会計の専門家として、数多くのフリーランス・企業の経営支援に従事している。
.png)

